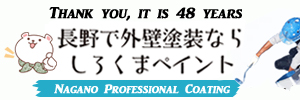「壁紙に黒いポツポツが…」「これってカビ?どうやって落とせばいいの?」
そんな疑問や不安を抱えたことはありませんか?
壁紙に発生したカビは、見た目が悪いだけでなく、放っておくとアレルギーや臭いの原因になることもあります。
でも、慌てて高い洗剤を買う前に、実は家にあるものでも十分にカビを除去できる方法があるんです。
この記事では、消毒用アルコールや重曹、キッチンハイター、ウタマロクリーナーなどを使った具体的な落とし方と、注意点、カビが再発しないための予防策までを丁寧に解説します。
Contents
壁紙のカビが落とせるアイテムとは?
まずは、「どんなアイテムでカビを落とせるのか?」という基本から押さえましょう。
以下の5つは、実際に壁紙のカビ除去に効果があるとされる代表的なアイテムです。
【1】消毒用アルコール(エタノール)
◆70〜80%のエタノール濃度が最も除菌力が高いとされています。
◆ティッシュやキッチンペーパーに染み込ませて、カビに押し当てたり、優しく拭き取るのが基本。
消毒用エタノールはカビの胞子を殺菌する力があります。
ただし、表面を漂白する効果はないため、色素沈着が残る場合もあります。
色柄付きの壁紙でも使いやすく、安全性も高いため、小さなお子さんやペットのいる家庭に向いています。
【2】食器用洗剤(中性洗剤)
◆水200mlに対して食器用洗剤を2〜3滴混ぜて、スポンジや布で優しく拭き取る。
◆表面汚れや軽度のカビに効果的。
強い洗剤を使いたくない方や、軽度のカビ汚れに向いています。
ただし、深く根を張ったカビにはやや効果が薄いため、早期のうちに使うのがおすすめです。
【3】キッチンハイター(塩素系漂白剤)
◆黒カビや頑固な汚れに強力な効果を発揮。
◆原液または2〜3倍に薄めた液を布に含ませ、カビ部分に押し当て、数分後に水拭きで仕上げ。
強力な除菌・漂白効果がある一方で、壁紙の色落ちリスクも高いため、目立たない箇所でテストしてから使用しましょう。
使用後はしっかり換気を行ってください。
【4】重曹スプレー
◆500mlの水に対して重曹をスプーン1〜2杯溶かし、スプレーボトルに入れて使用。
◆吹きかけてから数分放置し、拭き取ることでカビの除去に役立ちます。
重曹はアルカリ性の性質を持ち、カビの酸性成分と反応して分解します。
ナチュラルクリーニング派やアレルギーが心配な方におすすめ。重度のカビには不向きな場合もあります。
【5】ウタマロクリーナー
◆中性洗剤で、油汚れ・黒ずみ・カビにも効果的。
◆直接スプレーしてから布で拭き取り、しっかり乾燥させます。
壁紙にやさしい洗浄力で、安全性と使いやすさのバランスが良いのが魅力。
軽度~中程度のカビ除去に最適で、日常的な掃除にも使えます。
壁紙のカビ取りを行うときの注意点
「とにかく落とせばいい」と思って、安易に強い洗剤を使うと、逆に壁紙を傷めたり、体に悪影響を及ぼすリスクも。ここでは、カビ取り時の注意点を詳しく紹介します。
壁紙の素材に適したアイテムを選ぶ
◆ビニールクロスにはアルコールや中性洗剤が使いやすい。
◆布クロスや紙クロスには水分を吸収しやすい性質があるため、薬剤は最小限に。
◆凹凸のあるクロスは汚れが残りやすいため、丁寧な拭き取りが必要。
間違った薬剤を使うと、壁紙の変色・変形・剥がれの原因になります。まずは壁紙の種類を確認しましょう。
色落ち・変色テストを忘れずに
◆カビ取り剤は色柄壁紙に使うと色が抜けることがあります。
◆目立たない場所で「パッチテスト」を行うことで被害を防げます。
換気と手袋着用は必須
◆換気が不十分だと、塩素系の洗剤で気分が悪くなることも。
◆特にキッチンハイター使用時は、ゴム手袋・マスクの着用が必要。
カビが再発しないためにできる3つの予防策
カビは「落とす」よりも「生やさない」ことのほうが、実はずっと大切です。
せっかく掃除しても再発しては意味がありません。ここでは、カビの再発防止策を紹介します。
【1】湿度管理を徹底する
◆湿度が60%を超えるとカビが繁殖しやすくなります。
◆除湿器やエアコンのドライ機能を活用しましょう。
特に梅雨時期や冬場の結露が多い部屋では、湿度管理が再発防止のカギになります。
【2】定期的に換気を行う
◆カビの原因となる湿気やホコリを室内に溜めないことが重要。
◆換気扇やサーキュレーターも併用すると効率的。
空き家や長期間閉めきった部屋は特にカビが発生しやすいため、こまめな換気が必要です。
【3】壁紙の防カビコーティングも検討する
◆市販の防カビスプレーや防カビ剤で処理しておくと再発予防に効果あり。
◆壁紙張り替え時に防カビ機能付きクロスを選ぶのもおすすめです。
リフォーム予定がある場合は、最初から防カビ性の高い素材を選ぶことで長期的な対策ができます。
壁紙のカビがひどい場合はプロの力を借りるのも
軽度のカビであれば家庭用アイテムで十分対応可能ですが、下記のような場合には専門業者に依頼することを検討しましょう。
◆カビの範囲が広い(1㎡以上)
◆同じ箇所に繰り返しカビが発生している
◆壁紙の裏側までカビが浸食している
◆カビ臭が部屋全体に広がっている
専門業者は壁紙だけでなく、壁内部のカビや結露原因まで対応してくれる場合があります。
再発を防ぐには根本対処が必要です。
まとめ
壁紙に生えたカビは、放っておくと健康面や住宅の美観にも影響を与えます。
ただし、重曹・アルコール・ウタマロなど、家庭にあるアイテムで意外と手軽に対処できることも多いのです。
この記事のポイントまとめ
◆消毒用アルコールや重曹、ウタマロなどでカビは除去できる
◆塩素系漂白剤は強力だが色落ち・健康リスクに注意
◆壁紙の素材に応じて使う洗剤を選ぶことが大切
◆再発防止には換気・湿度管理・防カビ対策が有効
◆広範囲や重度のカビはプロに依頼するのが安心
まずは小さなカビから対処して、快適な住環境を取り戻しましょう。
自分でできることをしっかりやることで、大がかりなリフォームを防ぐことも可能です。