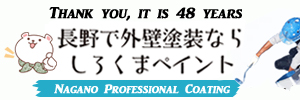確定申告で参考にしたい!飲食店の内装工事の耐用年数とは?長野市の内装業者が解説
みなさんこんにちは
『長野市の内装やさんの相談室』です。
飲食店を経営されている方の中には、「確定申告の際に分からない点がいっぱい出てくる」感じている人がいると思います。
税理士に委託をしない場合は会計処理も自分でしなければいけません。
開業前に行った内装工事はどのように計上すればいいのでしょうか。
今日は、法律が良く分からない、という方のために、飲食店の内装工事の耐用年数について解説していきたいと思います。
耐用年数とは
まず、会計処理の際の計算方法に、減価償却という手法があります。
これは、長期間にわたって所持する固定資産の取得に要した支出を、資産を使うことができる期間・年数に配分する、という計算方法です。
耐用年数とは、その「資産を使うことができる期間」のことです。
例えば、10年間使える機械(耐用年数が10年の機械)を1000万で購入したとします。
その購入した年に一気に1000万の費用として処理するのではなく、1年あたり100万円を費用として、10年間計上していくという計算方法です。
内装工事については、種類ごとに資産を計上して、適切な耐用年数で減価償却をしていかなければいけないという会計上の規定があるので、耐用年数をどのように考えればいいか、というポイントが問題になります。
内装工事の耐用年数
内装工事の仕訳は、請求書と明細書を参照しながら行います。
この時に、工事を「建物」、「建物付属設備」、「経費」のどれで計上するのかを確定します。
建物の構造、用途によって減価償却をする際の耐用年数が異なってくるため、登記事項証書などで確認しなければなりません。
事業を営んでいる場合、減価償却する際、税務署に届出をしていない場合は「定額法」に基づいて行うことになっています。
定額法とは、毎年一定額で減価償却費として計上する方法です。
先程の機械の例も定額法による計上です。
この場合、国税庁は飲食店の内装工事にかかる耐用年数と勘定科目を定めているので、それと実施した工事の内容を照らし合わせて、「建物」か「建物付属設備」のどちらに該当するのかを判断してください。
工事一式の金額が低い場合
取得価額が30万円未満である減価償却資産の場合、一度に経費として処理することができます。
ただし、この少額減価償却資産の特例は、期日までに「青色申告」の届け出が必要なので注意してください。
賃貸物件の場合
賃貸物件の場合は、賃借期間を耐用年数とする場合があります。
建物の耐用年数、内装工事の種類や用途、使用機材などを総合的に考慮して耐用年数を決めましょう。
最後に
今日は飲食店の内装の耐用年数についてお伝えしました。
是非この記事を参考にして、会計処理を行ってみてください。
 石井
石井
内装のことやリフォームのことなら長野市の内装やさんの相談室にお任せください。
フリーダイヤル 0120-460-461

◇メールでのお問い合わせはこちらから◇
・お問い合わせフォームに必要事項のご入力をして送信ボタンをクリックしてください。
・メールアドレスは正しくご入力下さい(弊社より返信メールが届きません。)
・【必須】の項目は必ず入力してください。
長野市内装工事・リフォーム施工エリア
長野市アークス 青木島 青木島町青木島 青木島町青木島乙 青木島町大塚 青木島町綱島 赤沼 県町 上ケ屋 浅川 浅川押田 浅川清水 浅川西条 浅川西平 浅川畑山 浅川東条 浅川福岡 旭町 安茂里 安茂里杏花台 安茂里小市 安茂里小路 安茂里米村 安茂里犀北 安茂里犀北団地 安茂里差出 安茂里大門 安茂里西河原 荒屋 石渡 泉平 伊勢町 伊勢宮 市場 稲里 稲里町下氷鉋 稲里町田牧 稲里町中央 稲里町中氷鉋 稲田 稲葉 稲葉上千田 稲葉中千田 稲葉日詰 稲葉南俣 稲葉母袋 居町 入山 上松 上野 往生地 大岡乙 大岡甲 大岡中牧 大岡弘崎 大岡丙 大橋南 大町 岡田町 小島田町 神楽橋 風間 合戦場 門沢 金井田 金箱 上駒沢 上千歳町 上西之門町 川合新田 川中島町若葉町 川中島町今井 川中島町今井原 川中島町今里 川中島町上氷鉋 川中島町原 川中島町御厨 川中島町四ツ屋 岩石町 北石堂町 北尾張部 北郷 北条町 北長池 北堀 狐池 鬼無里 鬼無里日下野 鬼無里日影 桐原 栗田 栗田北中 小柴見 小島 小鍋 権堂町 栄町 坂中 桜 桜枝町 桜新町 差出南 里島 早苗町 三才 三本柳西 三本柳東 篠ノ井会 篠ノ井石川 篠ノ井有旅 篠ノ井岡田 篠ノ井御幣川 篠ノ井杵淵 篠ノ井小松原 篠ノ井小森 篠ノ井塩崎 篠ノ井東福寺 篠ノ井西寺尾 篠ノ井布施五明 篠ノ井布施高田 篠ノ井二ツ柳 篠ノ井山布施 篠ノ井横田 下駒沢 下氷鉋 伺去 塩生 真光寺 信更町赤田 信更町上尾 信更町今泉 信更町桜井 信更町三水 信更町下平 信更町高野 信更町田沢 信更町田野口 信更町灰原 信更町氷ノ田 信更町古藤 信更町宮平 信更町安庭 信更町吉原 信更町涌池 信州新町上条 信州新町越道 信州新町里穂刈 信州新町下市場 信州新町新町 信州新町左右 信州新町竹房 信州新町中牧 信州新町信級 信州新町日原西 信州新町日原東 信州新町弘崎 信州新町牧田中 信州新町牧野島 信州新町水内 信州新町山上条 信州新町山穂刈 新諏訪 新諏訪町 新田町 新町 神明 末広町 諏訪町 台ケ窪 大門町 高田 田子 鑪 立町 田中 田町 丹波島 津野 妻科 鶴賀 鶴賀(居町) 鶴賀(上千歳町) 鶴賀(権堂町) 鶴賀(早苗町) 鶴賀(田町) 鶴賀(問御所町) 鶴賀(中堰) 鶴賀(七瀬) 鶴賀(七瀬中町) 鶴賀(七瀬南部) 鶴賀(西鶴賀町) 鶴賀(東鶴賀町) 鶴賀(緑町) 鶴賀(南千歳町) 鶴賀(峰村) 問御所町 戸隠 戸隠祖山 戸隠栃原 戸隠豊岡 徳間 富田 富竹 豊野町浅野 豊野町石 豊野町大倉 豊野町蟹沢 豊野町川谷 豊野町豊野 豊野町南郷 中越 中御所 中御所町 中条 中条日下野 中条住良木 中条日高 中条御山里 中曽根 長門町 七瀬 七瀬中町 七瀬南部 七二会乙 七二会己 七二会甲 七二会丁 七二会丙 七二会戊 西尾張部 西後町 西三才 西鶴賀町 西長野町 西之門町 西町 西和田 箱清水 花咲町 東後町 東犀南 東鶴賀町 東之門町 東町 東和田 平柴 平柴台 平林 広瀬 広田 穂保 真島町川合 真島町真島 松岡 松代温泉 松代町岩野 松代町大室 松代町小島田 松代町清野 松代町柴 松代町城東 松代町城北 松代町豊栄 松代町西条 松代町西寺尾 松代町東条 松代町東寺尾 松代町牧島 松代町松代 大豆島 檀田 みこと川 三ツ出 緑町 皆神台 南県町 南石堂町 南高田 南千歳 南千歳町 南長池 南長野(幅下) 南堀 宮沖 三輪 三輪田町 村山 茂菅 元善町 屋敷田 屋島 柳原 柳町 山田中 横沢町 横町 横山 吉 吉田 淀ケ橋 若里 若槻東条 若槻団地 若槻西条 若穂川田 若穂保科 若穂綿内 若穂牛島(1298〜1835番地) 若穂牛島(その他) 若松町 若宮